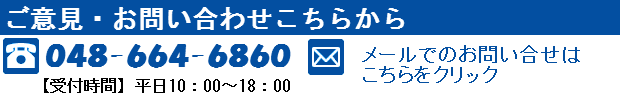弁理士の秘密保持義務・守秘義務:目次
弁理士の職務と秘密情報
知的財産権全般を取扱う資格
弁理士は、、主に「特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続」(弁理士法第4条第1項)についての代理をおこなう職業です。
また、「特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理」や「これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務」(同上)をおこなうこともできます。
さらに、知的財産権についてのいわゆるADR(裁判外紛争解決手続)における当事者の代理人、ライセンス契約の代理人、相談など、非常に広い範囲の知的財産権の職務をおこないます(弁理士法第4条第2項、第3項)。
弁理士が取扱う業務のうち、特に特許、実用新案、意匠に関する特許庁における手続については、秘密保持義務が極めて重要となります。
スポンサード リンク
弁理士の秘密保持義務・守秘義務
ある意味では最も秘密情報の取扱いに責任を負う資格
特許、実用新案、意匠を出願し、これらの権利を取得するためには、いわゆる「新規性」の要件が必要となります。「新規性」の要件を充たすためには、「秘密」であることが重要となります。
つまり、弁理士が特許、実用新案、意匠に関する手続きをおこなう場合、これらの情報を秘匿しておく必要があります。
当然ながら、弁理士からの情報漏洩によって、特許、実用新案、意匠の新規性が充たされないようなことになった場合は、その弁理士は、重い責任を負うことになります。
弁理士法にもとづく秘密保持義務
このようなことから、弁理士には、弁理士法第30条により、秘密保持義務が課されています。
弁理士法第30条(秘密を守る義務)
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この規定に違反した場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課されます(弁理士法第80条)。
依頼者との間にも善管注意義務にもとづく秘密保持義務が発生する
なお、弁理士法は、依頼者との関係を直接的に拘束する民事上の効果はありません。
ただ、一般的には、この規定や弁理士に課せられる善管注意義務を根拠に、弁理士は、依頼者に対して、当然に秘密保持義務を負っているとされます。
弁理士からの情報漏洩の可能性は低いが…
弁理士は、そもそも知的財産権や秘密情報を取扱う専門家ですし、不正競争防止法の専門家として情報の取扱いについて、依頼者に助言する立場にあります。
このため、現実的には、弁理士からの情報漏洩の可能性は、あまりないといえます。
従業員からの情報漏洩に注意
ただ、弁理士本人からの情報漏洩や情報の悪用の可能性が低いとしても、その従業員からの情報漏洩や情報の悪用の可能性までは、必ずしもないとはいいきれません(参照:大阪高裁判決平成18年10月5日。ただし、この判例では、従業員に対する競業避止義務は否定されています)。
さらに、弁理士本人が意図しなくても、サイバーアタックなどの不正アクセスにより、外部の第三者に情報が漏洩する可能性も否定しきれません。
情報を開示する前に対策を施しておく
このような実態から、依頼者の立場として、弁理士からの情報の漏洩や情報の剽窃、冒認出願などを気にする方もいらっしゃるようです。
ただ、そもそも弁理士に情報を開示するような段階では、弁理士からの情報漏洩・冒認出願の可能性以前の問題として、自身の従業員や第三者による情報漏洩・冒認出願の可能性の対策を検討しておかなけばなりません。
これらの情報漏洩・冒認出願への対策を取ることにより、結果として、弁理士への情報開示の段階では、その弁理士を含めた第三者からの情報漏洩への対策が取られている必要があります。
確定日付を活用して権利の保護を図る
具体的には、弁理士に開示する情報については、すべて書面化・データ化したうえで、その書面やデータを記録した媒体について、確定日付の手続きをおこなってください。
このような対策により、万が一、弁理士やその従業員からの情報漏洩があったとしても、いわゆる「新規性喪失の例外」による保護を受けることができる可能性が高くなります。
なお、この方法は、特許法上の先使用権を確保する意味でも、また、非公開の著作物の著作権を保護する意味でも、非常に重要です。
参照:公証制度の活用