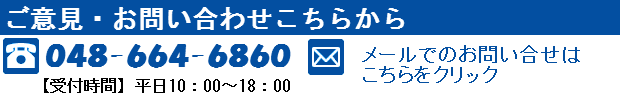単純ではあるが実現は困難
契約違反=債務不履行と不法行為が根拠
秘密保持契約にもとづく損害賠償請求は、他の契約と同じように、秘密保持義務条項の契約違反(=債務不履行)または民法上の不法行為が根拠となります。
契約実務上、損害賠償請求は、契約の性質によって、比較的簡単なものから困難なものまで様々ですが、秘密保持契約にもとづく損害賠償請求は、かなり困難なもであるといえます。
証拠集め・立証・損害の計算ともに難しい
というのも、漏洩した情報が秘密情報であることや、秘密情報の受領者の契約違反または故意・過失によって情報が漏洩したことなどを立証することが非常に困難です。
目に見えない情報の漏洩について、証拠をそろえて、しかも客観的に裁判で立証する作業は、あまり現実的であるとはいえません。
また、仮にこれらの立証ができそうであったとしても、損害の範囲や金額を計算することが非常に困難です。
漏洩した秘密情報によって現実に損害が発生していれば計算できないことはありませんが、未だ発生していない損害については、将来、秘密情報が拡散していってどこまで損害が拡大するのか、見当がつきません。
第三者に対する損害賠償請求は不法行為のみ
さらに、秘密保持契約の契約違反による損害賠償の請求は、あくまで契約当事者である受領者に対してしかおこなうことができません。
漏洩した秘密情報を第三者が勝手に使っていた場合は、秘密保持契約ではなく、民法上の不法行為を根拠に損害賠償請求をすることになります。
ただし、こちらは秘密保持契約の当事者である受領者ではなく、本来は無関係な第三者です。このため、受領者に対する損害賠償請求以上に難しいといわざるを得ません。
スポンサード リンク
秘密情報が営業秘密の場合は救済されやすい
秘密保持契約よりも手厚い保護を受けられる不正競争防止法
もっとも、漏洩した秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密である場合は、不正競争防止法を根拠に対策を取ることができます。
不正競争防止法を根拠にした場合は、秘密保持契約を根拠にする場合よりも、開示者は手厚い保護を受けることができます。
差止請求による秘密情報の使用の差し止めができる
まず、実際に営業秘密の漏洩があった場合において、その営業秘密が何らかの形で利用されている場合は、開示者は、差止請求等をおこなうことができます(不正競争防止法第3条)。
不正競争防止法第3条(差止請求権)
1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
損害の額について詳細な計算方法が規定されている
次に、損害額についても、計算方法が明確に規定されているため、開示者としては、秘密保持契約書にもとづく損害賠償請求よりも、比較的損害賠償の請求をしやすいといえます(不正競争防止法第5条)。
かなり長い条文なので、引用は割愛しますが、興味のあるかたは、以下のリンク先をご覧ください。
第三者に対する損害賠償請求もできる
さらに、開示者としては、不正競争防止法を根拠に、第三者に対して、損害賠償請求をおこなうこともできます。
不正競争防止法第4条(損害賠償)
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
(強調下線部は管理人による)
上記のとおり、損害賠償請求の対象者は、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者」であり、営業秘密を開示した当事者のみに限定されていません。
このため、第三者に対しても、損害賠償請求はできます。
秘密情報の保護は不正競争防止法の活用を中心にする
このほか、不正競争防止法を根拠にした場合は、秘密保持契約を根拠にした場合に比べて多くのメリットがあります。
このため、秘密情報を保護することを目的とした契約実務においては、事実上、不正競争防止法の適用を受けることを目的として、秘密保持契約を取り交わします。
損害賠償請求が簡単になる「損害額の予定」とは
あらかじめ損害額を決める条項
すでに述べたとおり、秘密保持契約にもとづいて損害賠償の請求をおこなう場合、損害額の計算が困難である、という問題があります。
このような問題を解決するひとつの方法として、秘密保持契約書に損害賠償の金額をあらかじめ記載しておく方法があります。これが、いわゆる「損害額の予定」という契約条項です。
損害額の予定とは、あらかじめ損害額を契約書で合意しておくことで、損害が発生した際に、その金額をもって損害額とすることです(民法第420条前段)。この金額は、裁判所ですら増減することはできません(同後段)。
民法第420条(損害額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
要するに、「罰金」を決めておく条項です。
情報漏洩の立証だけで損害賠償請求ができる
損害額の予定条項を秘密保持契約に設定することで、秘密情報の開示者は、損害の有無・多少を問わず、契約違反(=情報漏洩)を立証するだけで、受領者に対する、損害賠償請求ができます。
「損害額の予定」はあくまで最低限の金額とする
損害額は「固定」される
しかも、実際の損害額が損害額の予定の条項に規定した金額よりも少いと立証されたとしても、受領者が責任を免れたり、損害額が減額されることはありません(大審院判決大正11年7月26日)。
これは、開示者にとてはメリットであり、受領者としては、デメリットであるといえます。
ただし、逆に、実際の損害額が、損害額の予定の条項に規定した金額よりも多い立証されたとしても、開示者はその増額を請求することができません(大審院判決明治40年2月2日)。
これは、開示者としてはデメリットであり、受領者としては、メリットであるといえます。
損害額を最低限のものとすることもできる
この点について、最近では、損害額の予定の応用として、最低限の損害額を決めているる契約書を見かけます。つまり、予定された損害額よりも多い金額の損害が発生した場合は、開示者がその増額が請求できる内容の契約書です。
このような内容は、開示者にとっては一方的に有利な内容であり、逆に受領者としては一方的に不利な内容です。このため、契約条項として無効となる可能性も考えられます。
以上のようなメリット・デメリットがありますので、損害額の予定条項を規定する場合は、開示者・受領者ともに金額の設定に注意する必要があります。
なお、あまりにも高額な損害額の予定は、公序良俗違反として、無効となる可能性があります(大審院判決昭和19年3月14日)。