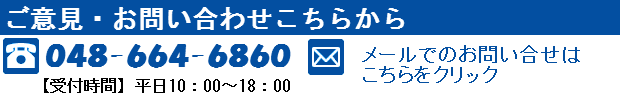ある行為の差し止めを請求する契約条項
差止請求とは、「ある行為の停止または予防」を請求できる契約条項のことです。不正競争防止法では、第3条第1項に規定されています。
不正競争防止法第3条(差止請求権)
1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
主に目的外使用を差し止めるための条項
秘密保持契約書における差止請求の請求は、目的外使用を差し止めるためにおこないます。
内容としては不正競争防止法第3条第1項の同様です。
例えば、製造請負契約に付随する秘密保持契約の場合、開示者=発注者の向けの製品の製造だけに秘密情報を使用してもよい、という条件となることがほとんどです。
にもかかわらず、受領者=開示者が、勝手に第三者のための製品の製造に秘密情報を使用しようとすることがあります。
これは、明らかに秘密情報の目的外使用です。秘密保持契約においては、秘密情報は明確に禁止されています。
参考:目的外使用の禁止
このような場合、秘密保持契約に差止請求の規定があれば、開示者は、受領者に対し、その第三者のための製品を製造する行為の停止や予防を請求することができます(ただし、これは秘密情報の性質によっては独占禁止法上問題となる可能性もあります)。
また、実際に第三者のために製品を製造してしまった場合は、その製造を停止するように請求することができます。
情報管理の徹底を求める根拠ともなりうる
なお、情報漏洩の「予防」という観点では、ずさんな秘密情報の管理を差し止める=やめさせるための条項としても機能する可能性があります。
参考:秘密情報の管理
スポンサード リンク
金銭賠償だけでは解決できない
秘密情報の漏洩や不正使用があった場合、損害賠償請求=金銭の賠償による解決は、実務上、非常に多くの困難が伴います。また、それ以上に、金銭賠償では問題が解決しないこともあります。
参考:損害賠償の請求
特に、金銭賠償は、実際に損害が発生しない限りすることができません。
つまり、上記の例のように秘密情報の目的外使用=契約違反があっても、実際に損害が発生していないのであれば、開示者は、裁判で金銭賠償の請求をしても認められない可能性が高いといえます。
このため、秘密保持契約書では、金銭による損害賠償請求以外にも、現におこなっている(または予定している)行為を「止めてもらう」という権利が重要となります。これが差止請求です。
ここでは、わかりやすい例として製造請負契約を掲げましたが、他の契約であっても同じことです。
不正競争防止法の保護がないことも想定する
すでに述べたとおり、差止請求と同様の規定として、実は不正競争防止法第3条第1項の規定があります。このため、あえて秘密保持契約書に差止請求を規定する必要性が低いようにも思われがちです。
しかしながら、あえて差止請求を秘密保持契約書に記載をすることには、非常に重要な2つの理由があります。
必ずしも不正競争防止法が適用されるとは限らない
第1の理由は、保護の対象となる秘密情報が営業秘密の要件に当てはまらない結果、不正競争防止法による保護がなされない場合に備える、という理由です。
確かに、秘密情報が不正競争防止法による保護を受けることができれば、それに越したことはありません。しかしながら、すべての秘密情報が、必ずしも不正競争防止法上の営業秘密であるとは限りません。
このため、不正競争防止法が適用されない、という最悪の事態を想定して、あえて秘密保持契約書にも差止請求の規定は記載します。
あくまで受領者に対してのみ行使できる
なお、不正競争防止法の差止請求については、開示者は、契約の当事者である受領者はもとより、第三者に対しても行使できます。
これに対し、秘密保持契約の差止請求は、契約の当事者間にしか効力が及びません。このため、契約当事者である秘密情報の受領者にしか行使できません。この点については、注意を要します。
契約として有効となるように契約書に記載する
第2の理由は、契約として有効となるように秘密保持契約書に記載する、という理由です。
本来は金銭賠償が原則
民法では、契約違反によってなんらかの損害が発生した場合、金銭による賠償が原則とされています(民法第417条)。
民法第417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
このため、差止請求については、「特別にこれを認める法律上の規定を有しない限り」許されないとされています(東京高裁判決平成3年12月17日)。
金銭賠償以外の救済の余地を残す
つまり、秘密保持契約書に差止請求の規定がなければ、金銭賠償以外の形による救済を受けることができなくなる可能性があるということです。
しかし、秘密保持契約書による当事者の合意があれば、例外的に、金銭による賠償以外の救済(差止請求を含む)を受けることができる、とも考えられています(ただし、この点については明確な判例があるわけではありません)。
開示者としては、裁判で差止請求を認めてもらうためにも、あえて秘密保持契約書にも差止請求の規定は記載するべきです。
なお、差止請求の規定は、受領者にとっては一方的に不利な条項ですので、なるべく記載しないか、削除してもらうようにしてください。