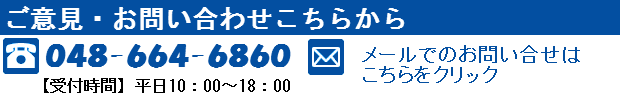特許の出願(新規性喪失の例外の利用):目次
情報漏洩=不正競争防止法による保護がなくなる
秘密情報が漏洩してしまうと、その情報は、公知の情報となってしまいます。これは、その情報が営業秘密の要件である「非公知性」を欠いてしまい、営業秘密として保護されなくなることを意味します。
もっとも、その秘密情報が営業秘密として認められる場合は、漏洩の経緯によっては、漏洩させてしまった者や漏洩後に勝手に情報を使用した者との関係で、不正競争防止法による保護を受けることができます。
しかし、その後は、公知の情報となってしまった情報は、営業秘密として保護されることは難しいといえます。
それでは、このように漏洩してしまった情報は、その後まったく保護することができないのかというと、必ずしもそうではありません。
情報漏洩があった後でも、特許法上の「発明」といえるような高度な秘密情報については、特許法による保護が期待できます。
スポンサード リンク
「発明の新規性喪失の例外」で特許を出願する
新規性=知られていない・実施されていない・公表されていない
秘密情報が特許を受けるためには、その秘密情報が、特許法第2条第1項の「発明」に該当する必要があります。発明の要件のひとつには、いわゆる「新規性」の要件があります(第29条第1項各号)。
特許法第29条(発明の要件)
1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
(1)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
(2)特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
(3)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
この新規性を充たすためには、発明が、公然と知られていない、公然と実施(≒使用・利用)されていない、出版やインターネットを通じて知られていない、という状態でなければいけません。
「新規性喪失の例外」により情報漏洩後の特許出願も可能
このような新規性の条件を満たしていれば、仮に発明の要件を充たした秘密情報の漏洩があったとしても、いわゆる「発明の新規性喪失の例外」(特許法第30条第1項)の制度により、開示者は、特許の出願をすることができます。
この制度は、発明が、「特許を受ける権利を有する者の意に反して」新規性を充たさない状態(公になった状態)となった場合、例外として、新規性を充たさない状態となった日から6ヶ月間だけは、新規性が喪失していないものとみなす制度です。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)
1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。
2 (以下省略)
(強調下線部は管理人による)
「意に反して」=秘匿・秘密保持の意に反して
ここでいう「意に反して」という点については、開示者が秘密保持義務を課しているかどうか、という点がポイントとなります(東京地裁判決平成17年3月10日)。
また、手続き上も、秘密保持契約書の存在が重要となります(特許庁;『平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集』平成23年9月 平成26年3月改訂 18ページ)。詳しくは、特許取得のリスクをご覧ください。
なお、この制度は、6ヶ月間というタイムリミットつきの制度です。このため、重要な秘密情報については、すぐに特許の出願ができるように、あらかじめ出願書類を作成しておいて、問題が起こった場合にすぐに対応できるような体制を整えておくことが重要です。
特許の出願→出願取下げを繰り返す
すでに述べたとおり、「発明の新規性喪失の例外」の制度により、情報が漏洩した場合であっても、その情報が技術情報であれば、特許出願をすることにより保護を受けることができます。
この制度を利用することにより、単に発明の新規性喪失の例外の適用を受けるだけでなく、さらに一歩進んで、より強力に秘密情報を特許として保護する方法があります。その方法が、特許の出願と公開前取下げを繰り返す方法です。
常に「出願中」の状態を維持し続ける
特許の出願は、原則として、出願の日から1年6ヶ月を経過すると、出願公開されます。出願公開があると、当然ながら、特許の出願をしている発明である秘密情報は、営業秘密の要件としての「非公知性」を失います。
しかしながら、出願公開の前に出願を取下げてしまえば、出願公開はされません。このため、特許の出願をしていた発明である秘密情報は、「非公知性」の要件を失うことなく、なお営業秘密として保護されます。
このような現行法の特許制度を利用することにより、常に特許出願がなされている状況を維持しつつ、営業秘密として情報を秘匿して保護することが可能となります。
発明の新規性喪失の例外のデメリットを解消できる
突然の情報漏洩にも対応できる
すでに述べたとおり、「発明の新規性喪失の例外」の制度は6ヶ月間のタイムリミットがあります。このため、秘密情報の漏洩があった場合には、慌てて対応せざるを得ません。
しかし、この方法だと、すでに出願していますので、粛々と対応することができます。
「先願」による独自発明への対応も可能
また、発明の新規性は出願の時点を基準に判断されます。
この点について、常に出願中を維持する方法は、「発明の新規性喪失の例外」とは違って、すでに出願そのものは終わっている状態となります。
このため、情報漏洩以外の事情による新規性の喪失(例:第三者の独自開発によってなされた同一の発明の公開)があった場合であっても、その新規性の喪失が出願の時点よりも後の場合は、なお新規性を失うことはありません。
これは、いわゆる「先願主義」(同一の技術については先に出願した者に特許権を付与する制度)を利用した考え方です。
出願を維持するためのコストがかかる
以上のように、この方法は、大きなメリットがありますが、デメリットもあります。まず、出願と公開前取下げを繰り返しますので、コストがかかるというデメリットもあります。
ただ、出願のための書類作成費については、1回分で済みます。また、秘密情報の漏洩や他者による特許出願が発覚しない限り、審査請求をおこなうことはありませんので、出願審査請求料も発生しません。
このため、2回目以降は、実質的には出願料(15,000円程度)のみがコストとなります。
秘密情報の価値にもよりますが、それほど高額というわけはありません。
出願日が繰り下がる
次に、この方法では、出願の都度、出願日が繰り下がっていきます。
先願主義を採用する我が国の特許法では、他者がより早く独自になした同一の発明について特許出願をしてしまうと、その他者が特許を取得してしまうリスクがあります。
ただ、これはまったく特許の出願をせずに、営業秘密として保護している状態でもいえることです。どちらかといえば、最初から特許を取得する場合と比較したデメリットといえます。
なお、他者に先願されて特許を取得された場合であっても、いわゆる「先使用権」により、一定の保護を受けることができます。