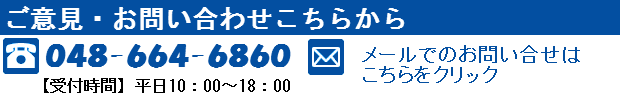業務委託先・外注先・下請けの監督義務:目次
最も情報漏洩のリスクが高い開示先
「業務委託先」の存在を常に意識する
企業間の取引において、契約当事者が契約を履行するために業務委託先を利用することはよくあることです。むしろ、契約当事者が単体で契約を履行することのほうが少ないケースであると思われます。これは秘密情報の開示がともなう契約であっても同様です。
他方で、日々報道されているように、業務委託先からの情報漏洩は後を絶ちません。ある意味では、業務委託先は、最も情報漏洩のリスクが高い情報の開示先であるといえます。
この点から、秘密情報の開示差者としては、受領者の業務委託先からの情報漏洩のリスクを常に考えなければなりまん。
業務委託先は「第三者」
ところが、秘密保持契約の契約当事者の項目でも解説したとおり、業務委託先は、厳密には契約当事者ではなく、第三者です。
このため、秘密情報の開示者は、受領者との秘密保持契約において、契約当事者でない受領者の業務委託先に対して、直接的に秘密保持義務などを課すことができません(ただし、三者間の契約として秘密保持契約を締結することは可能です)。
このため、開示者としては、原則として、受領者による業務委託先への秘密情報の開示を認めるべきではありません。
スポンサード リンク
受領者による業務委託先の管理監督義務
ただ、現実問題として、受領者による業務委託先への秘密情報の開示がなければ、契約の目的を達成できない可能性が高いといえます。
このような場合、開示者としては、受領者との秘密保持契約において、受領者に対して、業務委託先の管理監督を義務づけます。具体的には、次のような要求が考えられます。
- 開示者が認めた特定の業務委託先に対してのみ秘密情報の開示を認めること
- 再委託・孫請け等を禁止すること(後述)
- 業務委託先に対して秘密保持義務を課すこと
- 業務委託先に対して情報管理の方法等を指定すること
- 業務委託先や再委託先・孫請けなどが問題を起こした場合に受領者が責任を負うこと
もちろん、単にこれらの契約条項を規定したからといって、受領者が業務委託先を実際に管理監督できなければ意味がありません。
なお、これらの契約条項の内容があまりに拘束性が高く、受領者にとって不当に厳しいものであれば、契約条項として無効となる可能性もあります。
また、受領者としては、上記のような業務委託先に対する管理監督が過度になってしまうと、状況によっては、独占禁止法、下請法、労働者派遣法(偽装請負のリスク)などの関係で問題となる可能性もあります。
再委託先・孫請けの秘密保持義務
再委託先・孫請け等に対してはさらにガバナンスが働かない
開示者と受領者の取引の内容によっては、受領者の業務委託先が、再委託先や孫請けを使うことがあります。場合によっては、再々委託先、三次下請けなどに対して、更に業務委託をすることがあります。
このような再委託先や孫請けは、業務委託先と同様に第三者です。また、受領者と業務委託先の両者を間に挟んでいるため、開示者にとっては完全に部外者のようなものであり、業務委託先以上にガバナンスが働きません。
この点から、業務委託先よりも更に情報漏洩のリスクが高いといえます。
このような事情があるため、開示者としては、受領者に対して、業務委託先以上に、これらの再委託先や孫請けに対する秘密情報の開示を認めるべきではありません。
建設業者・システム(ソフトウェア)開発業者に注意
特に、再々委託や三次下請けなど、延々と業務委託を繰り返している業界の企業との契約を結ぶ場合、末端の事業者にまで秘密情報が拡散する可能性があります。このため、開示者としては、秘密情報の取扱い厳重に取決める必要があります。
これらの取引の代表的な例としては、建設工事請負契約とソフトウェア・システム開発契約があります。
工場のレイアウトの漏洩に注意
建設工事請負契約の場合、建設業者は、建設業法で秘密保持義務が課されていません。このため、秘密情報の管理が非常に杜撰になる傾向があります。
特に問題となるのが、製造業者が工場を建てる場合の、工場のレイアウト等の漏洩の問題です。
このような事情があるため、工場を建てる際の建設工事請負契約書には、しっかりと秘密保持義務や下請け・孫請けの管理監督を規定しておきます。
開示者として積極的に関与することも考える
ソフトウェア・システム開発業者(いわゆるベンダー)の場合、直接的に業界そのものを規制する法律すらありません。また、頻繁に情報のやりとりがおこなわれていますので、どうしても情報の管理は杜撰になりがちです。
特にリスクとして考えられるのが、顧客管理のシステム開発・運営の場合の、顧客情報の漏洩の問題です。
このような事情があるため、システム開発の際のシステム開発契約書には、しっかりと秘密保持義務や下請け・孫請けの管理監督を規定しておきます。
また、場合によっては、ユーザである開示者がプロジェクトマネジメントに積極的に関与して、秘密情報のコントロールや受領者(ベンダー)、下請け・孫請け等についても管理監督についても検討するべきです。