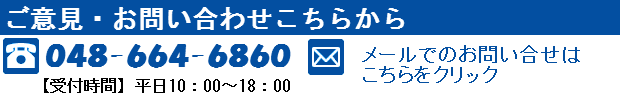外部専門家への情報開示:目次
法律上当然に秘密義務を負う有資格者
有資格者(士業)は当然に秘密保持義務を負う
企業経営に関わる外部専門家の多くは弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの、いわゆる「士業」と呼ばれる有資格者・国家資格者です。
これらの外部専門家は、刑法や各資格の業法(根拠法)によって、秘密保持義務や守秘義務が課されています。
このような刑法や業法にもとづく秘密保持義務や守秘義務は、あくまで外部専門家を規制する公法上の義務とされています。つまり、これらの法律は、士業とその依頼者との民事上(私法上)の直接的な秘密保持義務を規定しているわけではありません。
ただ、これらの外部専門家は、一般的には依頼者と(準)委任契約を結ぶことで依頼を受けます。
この(準)委任契約にもとづく善管注意義務(民法第644条)により、一般的には、外部専門家は、当然に依頼者に対して秘密保持義務を負うとされます。
民法第464条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
このため、一般的な企業や受領者の労働者・役員などに比べて、受領者が依頼している外部専門家による情報漏洩のリスクは低いといえます。
参考:秘密保持義務を負う職業
スポンサード リンク
「経営コンサルタント」に注意
ただし、いわゆる「経営コンサルタント」については、注意を要します。
「経営コンサルタント」には大きく分けて2種類あります。ひとつは、国家資格である「中小企業診断士」と、それ以外の無資格の経営コンサルタントです。
「中小企業診断士」は当然に秘密保持義務を負う
中小企業診断士については、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条7号で、間接的に秘密保持義務が規定されています。
これに対し、中小企業診断士でない無資格の経営コンサルタントについては、秘密保持義務や守秘義務を課している法律がありません。
自称「経営コンサルタント」は秘密保持義務を負わない可能性もありうる
いわゆる「経営コンサルタント」については、現在、中小企業診断士以外は国家資格は存在しません。このため、「自称」経営コンサルタントとして名乗ることができます。
無資格の経営コンサルタント自体は、直ちに違法であるとはいえませんので、少なくとも「経営コンサルタント」と名乗ること自体は、法律上の規制を受けることがありません。このため、必ずしも秘密保持義務や守秘義務が課されるとは限りません。
この点から、開示者としては、受領者に秘密情報を開示した場合に、受領者が依頼している中小企業診断士でない経営コンサルタントから情報が漏洩するリスクを考慮する必要があります。
また、受領者としても、中小企業診断士でない経営コンサルタントとコンサルティング契約を結ぶ場合は、必ず秘密保持契約を結ぶようにします。
外部専門家=受領者の味方
受領者の外部専門家の秘密保持義務は受領者に対する秘密保持義務
すでに述べたとおり、外部専門家には一定の秘密保持義務が課される可能性が高いといえます。しかし、開示者としては、安易に受領者が依頼する外部専門家に対する秘密情報の開示を許諾するべきではありません。
受領者が外部専門家に対して秘密情報を開示するということは、受領者が外部専門家になんらかの依頼をするということです。
すでに述べたとおり、外部専門家は、善管注意義務に従って、依頼者である受領者に対して、忠実に依頼を遂行する義務を負います。外部専門家は受領者の味方であって、開示者の味方ではありません。
つまり、外部専門家が秘密保持義務を負うのは、あくまで受領者に対してであり、開示者に対してではありません。
このため、秘密情報の外部専門家への開示は、受領者にとって有利な状況になることはあっても、開示者にとっては有利な状況になるとはいえません。
このように、単純に情報開示による影響を考えると、開示者としては、受領者による外部専門家に対する秘密情報の開示については、制限するべきです。
外部専門家といえども情報漏洩・開示のリスクはある
秘密保持義務=「情報管理体制の保証」ではない
また、いかに業法で秘密保持義務や守秘義務が課されているとはいえ、その外部専門家の職業倫理や事務所の情報管理体制によっては、情報漏洩のリスクがまったくないとまではいえません。
あくまで、外部専門家の秘密保持義務が規定されている秘密保持義務は、情報漏洩の抑止力として働くのみであり、情報管理体制の構築を義務づけるものではありません。
補助者=スタッフからの情報漏洩に注意
この点については、専門家本人からではなく、むしろ事務所の「補助者」、つまり従業員・スタッフに注意を要します。いかに専門家本人の職業倫理が高いといっても、実際に秘密情報に接する従業員・スタッフから情報が漏洩する可能性は、否定しきれません。
この点からも、開示者としては、受領者による外部専門家への情報開示については、安易に認めるべきではありません。
裁判による情報開示に注意
さらに、受領者が依頼する弁護士への情報開示については、訴訟になった際の情報開示のリスクもあります。
現在の日本の裁判は、公開が原則とされています。このため、万が一、受領者が裁判を起こした場合や、受領者が第三者から裁判を起こされた場合、弁護士に渡った開示者の秘密情報が裁判の過程で公開されるリスクがあります。
この点からも、開示者としては、特に受領者による弁護士への情報開示については、慎重に検討するべきです。