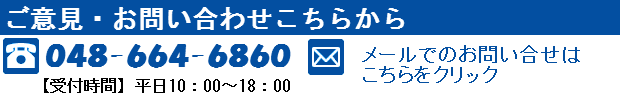秘密保持契約の契約当事者:目次
秘密情報は契約当事者以外が取扱う
「会社=役員・従業員」ではない
秘密保持契約に限ったことではありませんが、事業者間の契約の当事者は、法人です(個人事業者、任意組合、人格のない社団などの特殊なケースを除く)。
通常の事業者であれば、株式会社や有限会社が該当します。このため、秘密保持契約による秘密保持義務を負う主体は、法人そのものである株式会社や有限会社などです。
この点について、実際に秘密情報を取扱う当事者が問題となります。
秘密情報を取扱う主体は、制度上・観念的には法人となりますが、法人は物理的には存在しません。このため、実際に物理的に秘密情報を取扱う主体は人間(法人に対する概念として自然人といいます)です。
具体的には、法人の従業員や役員、業務委託先の従業員や役員、外部専門家など(以下、「関係者」とします)の人間が該当します。
このような関係者は法人そのものではありませんので、秘密保持契約の当事者ではなく、厳密には第三者であるといえます。
役員や従業員は「開示者に対しては」直接秘密保持義務を負わない
このため、これらの関係者は、理屈のうえでは、法人同士の秘密保持契約にもとづく秘密保持義務などを直接的に負うことはありません(ただし、役員や一部の管理職は、後述の民法第715条第2項により、開示者に対し直接損害賠償責任を負うことがあります)。
つまり、秘密情報の開示者としては、法人同士の秘密保持契約を根拠に、秘密情報の受領者の関係者に対して、直接的に秘密保持義務を負わせることはできません。
スポンサード リンク
従業員等による情報漏洩は第一義的には法人の責任
もっとも、受領者の従業員や役員が情報漏洩などの問題を起こした場合であっても、従業員や役員の行為だから受領者が開示者に対して責任を負わなくてもいいかというと、そうではありません。
一般的に、従業員や役員の行為は法人としての受領者の行為と考えられますから、その行為によって秘密保持契約違反が生じた場合は、法人としての受領者による秘密保持契約違反=債務不履行(民法第415条)となります。
また、受領者は、使用者(ここでは従業員等を「使用する者」という意味)として従業員等の監督責任を負います(民法第715条第1項)。
このため、実際に秘密情報の漏洩などがあった場合は、これらの法的根拠により、受領者(場合によっては役員や一部の管理職。同第2項)は、開示者に対して責任を負います。
ただし、受領者としては、情報を漏洩させるなどした従業員や役員に対して、その責任について求償することもできます(同第3項)
民法第715条(使用者等の責任)
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
従業員・役員は勤務先に対して当然責任を負う
他方、従業員や役員の立場としては、単に開示者に対して法人同士の秘密保持契約にもとづき直接的な責任を負う必要がないだけであって、使用者である受領者に対しては、労働契約(雇用契約)や委任契約にもとづいて、法的な責任を負うことになります。
参考:労働者の秘密保持義務、社員・従業員・パート・アルバイトの監督義務、役員・取締役・監査役の監督義務
受領者としては役員に直接損害賠償請求することも検討する
なお、役員が「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」は、開示者は、その役員に対して、直接責任を追求できる場合もあります(会社法第429条第1項)。
会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
1 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(以下省略)