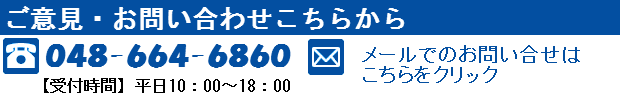公開された情報:目次
公開された情報は例外
公開された情報とは、「秘密保持契約の期間中」に開示者または第三者から公開された情報のことをいいます。
いわゆる「公知情報」との違いとしては、「秘密保持契約が成立した時点」で公知であったという点、つまりどの時点で公知であるのかが異なります。
公開された情報は保護する必要が乏しい
このような情報は公開されたものですから、仮にその後に秘密情報の受領者によって漏洩してしまったからといって、法的には保護に値しないものと思われます。
この点は、不正競争防止法上の営業秘密の要件として「非公知性」が求められている点と同様に考えるべきです。
また、公に知られてしまった情報であるにもかかわらず、これを秘密に保持するような秘密保持契約の義務は、契約上の義務としては、不当に厳しいものといえます。
このような事情から、一般的な秘密保持契約書では、公開された情報は秘密情報の例外として取り扱われることが多いようです。
公表されている知的財産権や人物の顔に注意
なお、公開された情報であっても、他の法律で保護される情報については、使用が制限されることがあります。
特に、特許権や著作権として保護される情報については、公開されたものであっても、勝手に使用すると、特許法違反や著作権法違反となる可能性もあります。
また、人物の顔写真などについては、個人情報の取扱いの問題や、肖像権、(著名人のものに限りますが)パブリシティ権などの人格権が発生する可能性がありますし、使い方によっては名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性もあります。
このため、取扱いは十分に注意するべきです。
スポンサード リンク
受領者による故意・過失による公開は秘密情報のまま
ただし、公開の方法によっては、開示者にとって意に反して開示されることがあります。このような公開のなかでも、特に問題となるのが、受領者の故意または過失による公開です。
例えば、過失の例としては、受領者の従業員の過失によって、インターネット上に顧客名簿が流出してしまった場合などが考えられます。
このような場合、いくら結果的に公開されてしまったとはいえ、そのことをもって公開された情報が秘密情報でないとされてしまうと、その後、開示者は、受領者との関係では、契約上の保護を受けることができなくなります。
このため、一般的な秘密保持契約では、受領者の故意または過失による情報の公開があった場合であっても、なおその情報は秘密情報として扱われるようにします。
なお、受領者の故意または過失により公開されたこと自体については、開示者は秘密保持契約や不正競争防止法による保護を受けることができる可能性があります。
情報公開の方法
開示者や第三者による「公開」とは、新聞、雑誌、書籍などの出版物による出版、テレビ、インターネットによるプレスリリース、学会、講演などでの発表、記者会見などによる公開などが考えられます。
これらの公開には、開示者の任意によるもの、メディアによる報道、法令(金融商品取引法など)にもとづくものなどがあります。
また、場合によっては、従業員からの漏洩、サイバーアタックなの不正アクセスによる公開のように、開示者の意に反した公開もありえます。
なお、開示者としては、特に情報の公開に制限がないかぎり、自由に秘密情報を公開できます。
逆にいえば、開示者としては、この公開にあたって、公開する「権利」がなければいけません。つまり、公開することが「秘密保持義務」に抵触しない必要があります。
情報公開の権利
開示者が情報を公開する場合、その情報が秘密情報でなければ、特に秘密保持義務違反となりません。
一般的な秘密保持契約では、例えば、開示者が保有している情報、いわゆる「保有情報」の公開であれば、秘密保持義務違反とはなりません。
「共有」の情報は公開できるか
この点について、問題となりやすい情報は、契約途中に発生した情報です。
このような情報は、必ずしもどちらかの契約当事者が一方的に開示できる情報であるとは限りません。いい換えれば、相互に秘密保持義務を負うことになる可能性があります。
代表的な例としては、共同研究開発契約における、研究結果などがあります。一般的な共同研究開発契約では、研究成果は秘密情報とし、相互に秘密保持義務を負うことになります。
このため、一般的には、研究成果は勝手にプレスリリースでの発表や学会での発表ができない契約内容となっています。
このような場合は、たとえ研究を担当した契約当事者といえども、相手方の承諾を得なければ、研究成果を公開できません。