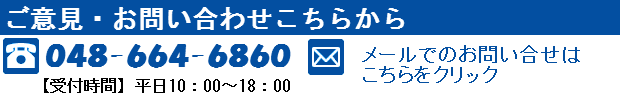営業秘密の要件1(秘密管理性):目次
「秘密として管理されている」こと
秘密管理性とは、その情報が「秘密として管理されている」(不正競争防止法第2条第6項)ことをいいます。
不正競争防止法第2条(定義)
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
(強調下線部は管理人による)
最も重要な営業秘密の要件
秘密管理性は、営業秘密の要件のうち、最も重要な要件です。というのも他の2つの要件(有用性・非公知性)に比べて、定義があいまいであり、必ずしも判定基準が明らかになっていないからです。
このため、過去の多くの裁判でも、ある情報が「秘密管理性」を充たしているかどうかを巡って争われてきました。その結果、判例のなかでは一定の方向性が定まってきています。
ポイントとしては、「その保有者が主観的に秘密にしておく意思を有しているだけではなく、従業者、外部者から、客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要」とされている点です(経済産業省;『逐条解説 不正競争防止法(平成23・24年改正版)』2012年12月5日)。
このため、開示者として秘密情報を保護する場合、いかに「客観的に秘密として管理されていると認められる状態」を創出するかどうかが重要となります。
スポンサード リンク
過去の判例の傾向
なお、過去の判例によると、秘密管理性を充たしているといえるほどの情報の管理状態のハードルは、非常に高いといわざるを得ません。後述の『営業秘密管理指針』によると、判例の秘密管理性の判断の傾向は、次のとおりです。
- アクセスできる者が限定され、権限のない者によるアクセスを防ぐような手段が取られている(アクセス権者の限定・無権限者によるアクセスの防止)
- アクセスした者が、管理の対象となっている情報をそれと認識し、またアクセス権限のある者がそれを秘密として管理することに関する意識を持ち、責務を果たすような状況になっている(秘密であることの表示・秘密保持義務等)
- それらが機能するように組織として何らかの仕組みを持っている(組織的管理)
秘密保持契約の実務においては、特に2が重要となります。
この点については、従業員向けの対策と、取引先向けの対策との両方が必要となります。特に、従業員向けの秘密保持契約書(秘密保持誓約書)については、秘密管理性が判断される際に、非常に重要な論点となることがあります。
『営業秘密管理指針』とは
このように、秘密管理性は、抽象的でわかりづらい部分があります。このような秘密管理性を充たすために参考となる資料が、経済産業省で策定している『営業秘密管理指針』です。
営業秘密管理指針は、「企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針」(「知的財産戦略大綱」)として、平成15年1月30日に策定されました。
その後、平成17年10月12日、平成22年4月9日、平成23年12月1日の3度の改定と平成27年1月28日の全面改訂を経て、現在に至ります。
参考:最新版『営業秘密管理指針』
最新の営業秘密管理指針では、それまでのものに比べて簡略化されていますが、基本的なポイントを押さえた読みやすい内容なっています。また、関連資料では、不正競争防止法の解説と秘密情報の管理のあり方が詳細に記載されています。
また、参考資料として、次の4点が付属していました(最新版には付属していません)。
営業秘密管理指針の活用による秘密管理性の向上
経済産業省のサイトで無料ダウンロード可能
営業秘密管理指針は、非常に実用性や有用性が高く、また、内容も充実していて、多くの企業にとって参考になる資料です。しかも、経済産業省のサイトで無料でダウンロードできます。このため、非常に気軽に活用することができます。
参照:営業秘密 〜営業秘密を守り活用する〜(METI/経済産業省)
実際に秘密情報を営業秘密として保護しようとする場合、秘密管理性を充たすかどうかが、事実上唯一の重要なポイントであるといえます。
このため、この『営業秘密管理指針』を参考に、秘密管理性を向上させ、秘密情報を管理するべきです。
契約書の参考例はあくまで「参考」程度に
ただし、上記の参考資料2の「各種契約書等の参考例」については、あくまで参考例ですから、必ずしも個別の契約内容に適合しているとは限りません。
このため、実際に利用する場合は、これから締結しようとしている契約の実態に適合しているかどうかを慎重に見極めたうえで利用してください。