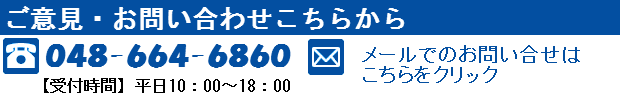違約金・賠償額の予定が重要
秘密情報の漏洩や不正使用があった場合、その損害についての算定が非常に難しいといえます。
このため、秘密情報の開示者としては、損害額の算定を容易にするために、契約実務上は、違約金や損害額の予定を設定することがあります。これにより、損害額の計算方法をあらかじめ確定させることができます。
逆に、このような規定がないと、実際に秘密情報の漏洩や不正使用があった場合に、その漏洩や不正使用の事実そのものについて当事者間では争いがなかったとしても、損害額で協議がまとまらないことになります。
この結果に、秘密情報の開示者としては、泣き寝入りをせざるを得なくなる可能性もあります。
スポンサード リンク
秘密保持契約書には損害賠償の金額を明記する
秘密情報そのものの価値や、情報漏洩の際の損害額の正確な算定は、非常に難しいといえます。
このため、実際に情報が漏洩してしまった場合に、どのような根拠にもとづいて損害額を算定するかを、あらかじめ検討しておく必要があります。
参考:秘密情報の価値
民法第420条により損害額をあらかじめ決めておくことができる
一般的に、なんらかの損害が発生した場合、その損害額は、原則として、その都度計算されます。これは、当事者間で合意したうえで決定することもあれば、第三者(裁判所・仲裁人)が決定することもあります。
ただし、例外として、契約実務上、あらかじめ損害賠償の金額を契約で決定しておくことができます。これを、「損害額の予定」(民法第420条)といいます。これは、情報漏洩の損害としての金額をあらかじめ契約で合意しておくことを意味します。
民法第420条(損害額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
この損害額の予定を秘密保持契約書において規定することにより、情報の漏洩があった場合に、スムーズに対応することが可能となります。このように、損害額の予定は、情報漏洩の際の損害額の算定が困難な点を解決するひとつの方法です。
なお、損害賠償の予定には、必ずしもメリットばかりがあるとは限りません。デメリットもありますので、その利用には注意を要します。詳しくは、損害賠償の請求をご覧ください。
交渉が難航する場合は計算方法を規定する
契約実務上、損害額の予定の規定は具体的な金額が規定される条項であるため、交渉が難航することが多く、結果として、契約交渉が暗礁に乗り上げることがあります。場合によっては、破談となることもあります。
このため、具体的な金額を規定するのではなく、損害額の計算方法を規定することにより、妥結することも検討に値します。例えば、特許法第102条、不正競争防止法第5条、著作権法第104条等の規定に類似するような条項を規定することが考えられます。
ただ、実務上は、このような計算方法ですら合意に至らないことが多いです。このため、結局は損害賠償の金額や計算方法は明記しない秘密保持契約書となります。
この点から、万が一、秘密情報が不正使用され、または漏洩したときは、上記の不正競争防止法第5条による保護を受けられるように、対策を講じておく必要があります。
労働契約書・雇用契約書には明記しない
労働者・従業員・社員に対する「罰金」は「犯罪」
労使間の労働契約・雇用契約では、労働基準法第16条により、違約金や損害賠償額の予定の設定が禁止されています。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
違約金や損害賠償額の予定を労働契約書・雇用契約書で規定した場合は、(単に規定しただけでも)6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性もあります(労働基準法第119条第1号)。
労働基準法をご存知でない経営者がやりがちなパターンですが、安易な感覚で「罰金」や「ペナルティ」を設定した場合は、犯罪となります。
このため、労働契約・雇用契約において、労働者・従業員による秘密情報の不正使用や漏洩に関して、違約金や損害賠償額の予定による損害額の算定は利用できません。
ただ、これは、あくまであらかじめ金額を決めておくことができないだけです。実際に損害が発生した際には、使用者は、損害賠償の請求そのものはできます。
秘密保持契約は金銭賠償の根拠ではなく、あくまで抑止力
もっとも、一個人である労働者による損害賠償には限度があります。このため、損害賠償請求の根拠としては、あまり秘密保持契約書や秘密保持誓約書は機能しません。
むしろ、情報の漏洩を抑止する手段の一つとして、秘密保持契約書・秘密保持誓約書の利用を検討するべきです。