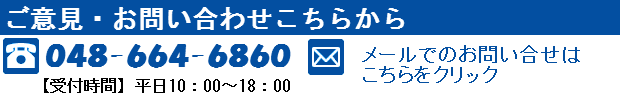すべての情報を秘密情報とする方法:目次
包括的な秘密情報の定義
「ぜんぶ秘密情報」
開示するすべての情報を秘密情報とする定義は、文字通り、開示するすべての情報を秘密情報とします。いわば「包括的」な秘密情報の定義といえます。
例えば、次のような規定が考えられます(出典:経済産業省;『営業秘密管理指針』2003年1月30日(2015年1月28日全面改訂) 参考資料2 各種契約書等の参考例』第8を一部改変)。
第○条(秘密情報)
本契約において、秘密情報とは、甲が開示するすべての情報及び本契約の履行により生じる情報をいう。
このような方法は、契約実務上は、秘密保契約書に簡単に定義づけることができる、というメリットがあります。
このため、一般的な秘密保持契約書では、よく採用されている方法です。
スポンサード リンク
全情報を秘密情報とするメリット
このほかにも、契約実務上、情報の開示者にとって、いくつかのメリットがあります。
第1に、非常に広い範囲の情報を秘密情報とすることができる、という点です。開示する情報をすべて秘密情報とするため、これは当然のことです。
第2に、開示する情報をそのつど秘密情報として指定する必要がない、ということです。
開示の時点では非常に「楽」な方法
秘密情報の定義の方法には、開示する内容のうちの一部の情報を秘密情報として指定する方法があります。このような方法では、いちいち開示する情報について秘密情報とするかどうかを検討し、秘密情報とする場合はその旨を指定しなければなりません。
これに対して、開示する情報のすべてを秘密情報とする方法では、このような煩わしい検討・指定をおこなう必要はありません。
秘密情報の開示者側のデメリット
すべての情報を秘密情報とする方法については、秘密情報の開示者側のデメリットとしては、次のようなものがあります。
楽な方法=「管理していない」=秘密管理性が否定される
この方法では、開示する情報をすべて秘密情報とするため、情報を管理しているとはいえないと解釈される可能性があります。
このような解釈が成り立つ場合、開示された情報について、営業秘密の要件のひとつである秘密管理性を否定する要素となる可能性があります。
つまり、開示するすべての情報を秘密情報として定義づけた場合、その情報は秘密管理性がないものとされ、営業秘密として保護されない可能性があります。
また、このような方法は、あまりに秘密情報の範囲が広く、秘密保持義務が非常に厳しい内容となるために、場合によっては、民法上の公序良俗違反(民法第90条)として、秘密保持義務が無効となる可能性があります。
秘密情報の受領者側のデメリット
他方、秘密情報の受領者側のデメリットとしては、次のようなものがあります。
秘密保持義務の範囲が広くなる
まず、秘密情報の範囲が広いため、結果として、秘密保持義務の範囲も広くなる、というデメリットがあります。
これは、単純に情報漏洩のリスクが高くなる、という問題にとどまらず、管理のためのコストもかかるという点から、問題といえます。
ぜんぶ秘密情報=どれが秘密情報?
次に、情報管理が杜撰になる可能性がある、というリスクもあります。一般的に、秘密保持契約の契約交渉の担当者は、秘密情報の定義や秘密保持義務の内容を理解していますが、実際に秘密情報を取り扱う者は、必ずしもそうであるとは限りません。
このため、本来は、秘密保持契約の内容や秘密情報の定義を周知徹底したり、開示する資料にマル秘マークを付けたりすることによって、秘密情報の取扱いについての注意を喚起する必要があります。
しかしながら、開示するすべての情報を秘密情報とした場合、(開示者もそうですが)特に受領者の側で管理を徹底して注意喚起をしなければなりません。
そうしないと、特に現場の従業員は何が秘密情報に該当するのかがわかりません。これは、結果として、かえって秘密情報の管理が杜撰となる可能性があります。
なお、受領者の情報管理が杜撰となる可能性があるということは、情報漏洩のリスクも高くなるということであり、結果的には、開示者にとってもデメリットであるともいえます。
あくまで他の方法では難しい場合に限定して使う
このように、包括的な秘密情報の定義は多くの問題点がありますので、他の方法で秘密情報を定義づけることが難しい場合に、例外的に活用する程度にとどめておくべきです。