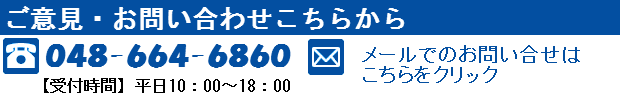記録媒体で秘密情報を特定する:目次
秘密情報が具体的に特定される非常に優れた方法
記録媒体で秘密情報を特定する方法は、秘密としたい情報が記録された媒体を指定することによって秘密情報を特定する方法です。このため、特定の媒体のやりとりを通じて情報を開示する契約に向いた方法です。
具体的には、次のような記載となります(出典:経済産業省;『営業秘密管理指針』2003年1月30日(2015年1月28日全面改訂) 参考資料2 各種契約書等の参考例』第8を一部改変)。
第○条(秘密情報)
本契約において、秘密情報とは、ラボノートXに記載された情報をいう。
第○条(秘密情報)
本契約において、秘密情報とは、Y社から提供されたファイルZのうち○○ページに記載された情報をいう。
これらの記載例は、いずれも従業員向けの秘密保持契約書の場合の例ですが、企業間の秘密保持契約書でも使用できる表現です。
スポンサード リンク
記録媒体で情報が特定されるメリット
この方法による秘密情報の定義は、具体的に情報が特定される、というメリットがあります。
情報が特定される方法としては、この他には、クレーム類似形式や詳細な記載により、個別具体的に記載する方法しかありません。
「開示した」記録が重要
もっとも、実際に秘密情報の漏洩や目的外使用があった場合には、どの記録媒体を開示したのか、という客観的な記録が残っていなければ、開示者は、契約違反を主張することができません。
このため、開示者が情報を開示する際には、記録が残る形で情報を開示する必要があります。
「秘密管理性」が認められる要素となりうる
また、記録媒体で秘密情報を特定する方法による秘密情報の定義は、開示された情報について、営業秘密の要件のひとつである秘密管理性を肯定する要素となる可能性があります。これは、もっぱら、開示者側にとってのメリットとなります。
なお、この方法は、クレーム類似形式・詳細な記載の方法と併用することで、より情報を特定することができます。
受領者側の情報管理に要注意
記録媒体で秘密情報を特定する方法は、開示の方法によっては、受領者側による情報管理が杜撰になる可能性がある、というリスク・デメリットがあります。
現場の従業員にも秘密情報であることがわかるようにする
一般的に、秘密保持契約の契約交渉の担当者は、秘密情報の定義や秘密保持義務の内容を理解していますが、実際に秘密情報を取り扱う従業員は、必ずしもそうであるとは限りません。
このため、開示者としては、単に契約書で記録媒体と特定するだけではなく、実際に開示する記録そのものについても、秘密である旨がわかるように注意書きやマル秘マークをつけるなどして、受領者側の秘密情報の取扱いについての注意を喚起する必要があります。
なお、受領者の情報管理が杜撰となる可能性があるということは、情報漏洩のリスクも高くなるということであるため、結果的に、この点は、開示者・受領者の双方にとってデメリットとなります。
口頭での開示に注意
記録されてない情報=秘密情報ではない
また、この方法は記録媒体による秘密情報を特定しているため、媒体に記録されていない情報については、秘密情報として扱われません。
このため、例えば、口頭によって開示された情報は秘密情報とされません。これでは、電話や会議での発言などが秘密情報とみなされないことになります。
また、媒体に記録することができない情報(例:やや特殊な例ですが、味覚、嗅覚、触覚等により知覚できる情報など)についても、秘密情報として取り扱われない可能性もあります。
このため、何らかの方法で、媒体に記録さずに開示された情報であっても、開示後に秘密情報とできるような対策が必要です。