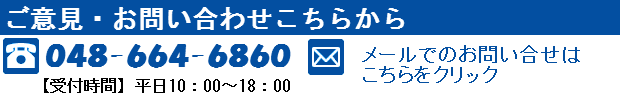目的条項とは
普通の契約ではあまり重要ではない
目的条項とは、契約の全体的な内容や趣旨を総論的に規定する条項です。このため、その他の個々の契約条項に比べて、さほど重要視されることはありません。
それどころか、中には、目的条項で高尚な理念などを謳っている契約書などもありますが、実際の契約実務では特に効果はありません。
一般的な契約において、目的条項が問題となるのは、契約書に記載されていない事態が発生した場合です。
このような場合は、契約の趣旨を解釈するために、目的条項を参考することがあります。このような場合以外では、目的条項は、あまり注目されることがありません。
スポンサード リンク
重要なことは「目的の定義」
秘密保持契約では特に重要な「目的条項」
ただ、一般的な契約書とは違って、秘密保持契約書においては、目的条項は非常に重要となります。
秘密保持契約書では「目的外使用の禁止」という条項があります。この条項に関連して、「目的外使用の禁止」の「目的」とは何か、という点が問題となることがあります。
「目的」が契約違反の基準となる
要するに、「目的」に合った秘密情報の使用はセーフですが、目的に合っていない秘密情報の使用はアウト、つまり契約違反となります。
ということは、「目的」の定義が明確でないと、目的外使用の禁止の条項に違反するのかどうか=契約違反の基準が明確になりません。このため、秘密保持契約の目的を契約書に明確に記載する必要があります。
目的条項では、この秘密保持契約の目的を明記します(当然、他の条項に規定しても差し支えありません)。
このように、秘密保持契約書においては、目的条項が重要となります。このため、目的条項を軽視することなく、慎重に検討のうえ、目的にの定義を明記する必要があります。
なるべく具体的・明確に記載する
抽象的な理念は記載は無意味
すでに述べたとおり、目的の定義は、目的外使用の禁止に抵触するかどうかの基準となります。このため、目的条項を記載する際には、なるべく具体的・明確に記載する必要があります。
よく一般的な契約書にありがちな、「信義誠実の原則に従って…」や「共存共栄のために…」などのような、抽象的・理念的な記載では不十分です。
このような規定は、契約書の格調を高める程度の意味はあるかもしれませんが、法的には特に意味はありません。
このような抽象的・理念的な記載ではなく、具体的に何のために情報を開示し、秘密情報の使用の許諾と限定をし、秘密保持義務を課すのか、という点を明記します。
開示者としては狭く・受領者としては明確に
開示者としては「ポジティブリスト」で限定的に記載する
この際、開示者としては、目的はなるべく狭く、限定的に、かつ、明確に規定するべきです。というのも、あまり目的を広く、曖昧に規定してしまうと、受領者に目的を拡大解釈されてしまう可能性があるからです。
この際、常に「不正使用される」可能性を念頭におき、どのようになら使っていいのか、という「ポジティブリスト」の考え方で、限定的・具体的・明確に目的を記載します。
また、場合によっては、想定される「不正使用」について、あらかじめ契約書においてリスト化し、そのような使用が「目的に合っていなない}=「契約違反」であるとを明記することも検討してください。
受領者としては想定している目的の範囲で明確に
他方、受領者としては、目的をなるべく広く規定するべきです。
受領者としては、契約の履行に必要な範囲で目的を規定し、情報の使用にあたって、目的外使用とならないようする必要があります。このため、想定している情報の使用が目的外使用とならないように、目的を明確に規定することが最も重要な点となります。
その意味では、必ずしも目的の範囲を広く規定する必要まではありません(当然ながら想定する秘密情報の使用が目的に含まれていることが前提です)。
ただ、契約期間中に、秘密保持契約を取り交わした当初に想定してなかった使用をしなければならなくなる可能性も否定できません。このため、可能であれば、目的を広く規定することも検討するべきです。