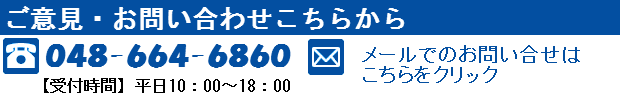秘密情報の不正使用の防止を担保する条項
情報の不正使用はリカバリーが難しい
受領者との間で秘密保持契約を結んだ場合には、秘密情報の不正使用があったとしても、契約や不正競争防止法により、開示者は、ある程度は救済されます。
しかしながら、実際に救済されるためには、裁判を起こして、煩雑な手続きや困難な立証作業をしなければなりません。
しかも、不正競争防止法にもとづく一定の保護手続き(いわゆる「インカメラ審理」など)を経ない限り、裁判は原則として公開されますので、秘密情報も公開されてしまう可能性もあります。
このため、不正使用がおこった場合の対策と併せて、そもそも情報が不正使用されないような状況になければなりません。その具体的な方法のひとつが、「競業避止義務」です。
スポンサード リンク
競業避止義務とは
自社と競業する事業そのものを禁止
競業避止義務とは、秘密情報の受領者が開示者と同様の事業をおこなうことを禁止する条項です。
競合避止義務は、ある意味では、目的外使用の禁止を一段と厳しくした義務といえます。このため、受領者にとっては、非常に拘束性が高い条項であるといえます。
競合避止義務を課すことにより、開示者は、受領者が秘密情報を不正使用してライバル企業として事業活動をおこなうことそのものを制限することができます。
これは、受領者にとっては、開示者のライバル企業として秘密情報の不正使用ができる状況の創出そのものが禁止されることになります。この結果、秘密情報が不正使用される可能性が非常に低くなります。
非常に厳しく反発必至の規定
ただ、競業避止義務は、受領者から反発される可能性が高い条項です。特に、同業者間の契約に付随する秘密保持契約の場合は、事実上規定することができません。
また、競業避止義務は、あくまで不正使用の防止を目的としたものですから、情報漏洩の防止のためには、あまり効果がありません。
競業避止義務は無効となる可能性が高い
競業避止義務は、開示者にとっては非常に都合のいい条項ですが、受領者にとっては、拘束性が極めて高い条項であるといえます。このため、競業避止義務の契約条項は、法的には無効となる可能性も否定しきれません。
「憲法違反」の競業避止義務?
特に、競業避止義務は、憲法で保証されている「職業選択の自由」や「営業の自由」との関係や独占禁止法上の問題もあります。このため、過去の判例では、必ずしも競業避止義務が有効と判断されているわけではありません。
このような事情を踏まえ、実際に競業避止義務を秘密保持契約書に記載する際には、過去の判例の傾向を踏まえて、契約条項として有効となる競業避止義務を起案する必要があります。
有効となる競業避止義務と判例の傾向
なお、過去の判例の傾向では、競業避止義務の有効性が争われた事案としては、次の5点が論点となっていることが多いようです。
- 競業避止義務の代替措置としての見返りがあるかどうか
- 競業避止義務の期間が適切かどうか
- 競業避止義務の地理的範囲が適切かどうか
- 競業避止義務の業種が限定されているかどうか
- 競業避止義務が規定されている契約の締結手続きが適切かどうか
実際に競業避止義務を秘密保持契約に規定するには、以上の点を考慮したうえで、代替措置を講じ、期間、場所、業種を適切に限定します。さらに、適正な手続きに従って契約を締結してください。
このような秘密保持契約の内容・手続きとすることで、競業避止義務が無効となるリスクを抑えることができます。
必ず有効になるわけではない
もっとも、上記の1〜5のすべてを充たした秘密保持契約書を用意して適正な手続きに従って契約を締結したからといって、必ずしも競業避止義務が有効と認められるわけではありませんので、注意してください。
余談ですが、フランチャイズ契約においては、競業避止義務は比較的認められやすい傾向があります。